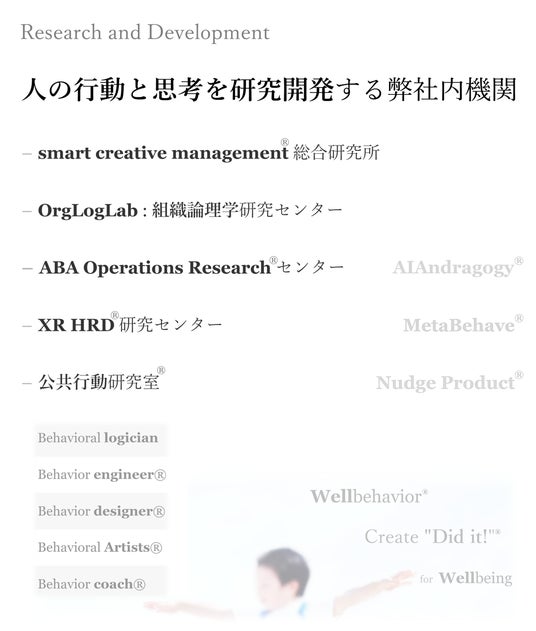プレスリリース
33.8万人の行動データが解明 ─ 誰もが自然に、“お客様に必要とされる”、“部門を越えて共働する”といった意味ある行動を続けられる組織をつくる「組織行動科学(R)」を正式発表
リリース発行企業:リクエスト株式会社
全国の企業で今、静かに広がる課題があります。
- 会議で前向きな意見が交わされても、現場の動きには反映されない
- 研修で身につけたスキルも、使われずに棚に置かれたまま、以前のやり方で仕事が進む
- 経営層が社会的に意義のある目的を掲げ、その実現方針を伝えても、現場は従来の役割分担にとどまり、日々の行動は変わらない
- さらに、部門間の情報共有や共働も、形だけの会議や報告に終わり、実際の行動や成果にはつながらない。
こうした“静かな生産性低下”の原因は、意志やモチベーションの不足ではなく、行動を自然に続けられる「構造」が欠けていることにあります。
リクエスト株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役 甲畑智康)は、この課題を解決するため、延べ33万8,000人・980社の現場データを分析し、「組織行動科学(R) 理論体系」を構築しました。
本体系は、意志や根性に頼らず、お客様や取引先が善くなる行動を自然に続けられる仕組みであり、日本企業を少しでも善くし、その先に“信頼と意味が巡る社会”を実現することを目的としています。さらに、生成AIとの共働構造を統合し、短期的な行動変化と長期的な価値観進化を両輪で実現します。
「組織行動科学(R)」とは
人の行動が「なぜ起こり」「なぜ続くのか」を、5つの理論領域(行動制御理論・動機/報酬理論・関係構築理論・認知/思考理論・習慣形成理論)で解明し、誰が実行しても成果を再現できる“行動の設計図”としてまとめたものです。特に重要なのが、心理的リワード(心の報酬)です。これはお金や物ではなく、「できた!(達成感)」「役に立てた(貢献実感)」「認められた(承認・共感)」「成長できた(成長実感)」といった感覚で、これらが一定の順序で巡ると、行動が持続し、文化として根づくことがわかっています。
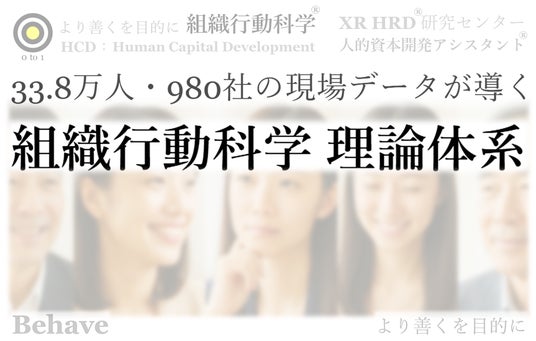
社会的背景
会議では前向きな意見が出ても、現場に戻れば動きが止まる。研修で学んだスキルも、数か月後には元に戻る。あなたの会社でも、思い当たる場面はないでしょうか。こうした「やればできるのに、続かない」現象は、今や多くの企業で日常的に起きています。
問題の根本は“やる気不足”ではありません。日々の行動を自然に続けさせる構造の欠如です。本来、組織が変化に適応し進化するには、次の巡環が不可欠です。
- 変化を経験する
- 経験から事実を抽出する
- 事実の背景にある構造を想定する
- そこから目的をイメージで構想する
- 現状とのギャップを問題として設定
- その問題を共に解決していく
この巡環は「制度に馴染みながら制度を超える人材」の習慣。
しかし、多くの組織は役割分担と効率化を優先しすぎた結果、この巡環の初期段階、経験から事実を抽出し、背景構造を考える部分が省略されています。その結果、構造を捉えて目的を再設定できる人材が減り、組織は次の三類型に偏る傾向があります。
- 制度破壊型(約1~3%)既存の枠組みにとらわれない視点を持つ人材に多い。組織の惰性を打破する可能性を秘める一方、周囲の理解や支持を得られず孤立しやすく、変革が属人的になりやすい。
- 制度依存型(約60~70%)制度や手順を忠実に守ることを優先し、安定運営に貢献する人材が多い。ただし変化への適応は遅れやすく、想定外の事態や新しい挑戦には消極的になりやすい。
- 日和見型(約25~35%)状況や周囲の空気に応じて立場を変える傾向を持つ。対立を避けるために現状維持を選びやすく、明確な方向性を持つ人材が不在の場合は行動が停滞しやすい。一方で、環境やリーダー次第では変革側にも安定側にも動ける柔軟性がある。
- ※ この比率は、厚生労働省「雇用動向調査」や大手人材会社の転職動向データ、さらに延べ980社以上・33万人超の現場観察(組織行動科学(R)プロジェクト)をもとに推定しています。大手企業ではこの傾向が安定的に見られます。
こうした状況下では、単に方針を示し、KPIで管理し、頑張るように発破をかける、あるいは研修でスキルを教える、といった従来型マネジメントでは限界があります。これらは一時的な行動を引き出すことはできても、行動が自然に続くための組織的循環を生み出すことはできません。
だからこそ必要なのが、誰が実行しても同じ成果が再現でき、現場の中で巡環を止めずに回し続けられる構造的アプローチです。本理論体系は、そのための「実践可能な設計図」として構築されています。次に、その特徴を紹介します。
理論体系の特徴
1. 33.8万人・980社の行動データに基づく実証モデル
延べ33万8,000人・980社から収集した現場データを匿名化・蓄積。統計解析・テキストマイニング・行動ログ分析を組み合わせ、行動の持続条件を科学的に抽出しました。Quick-Q(週2回の短時間問いかけ)、日報記述の意味語解析、1on1応答ログ、再実行までの時系列変化など、現場での“生きた行動”を直接分析しています。
2. 5つの理論領域による多面的アプローチ
行動制御理論/動機・報酬理論/関係構築理論/認知・思考理論/習慣形成理論の5領域を統合。行動の起点(やってみる)から定着(続けられる)までを一貫して設計できるため、特定の業種や文化に依存せず再現性が高いのが特徴です。3. 心理的リワード(心の報酬)の巡環構造
お金やモノではなく、「できた!」「役に立てた」「認めてもらえた」「成長できた」といった感覚が、行動を自然に続けたくなる心の報酬=心理的リワードです。達成感・貢献実感・承認共感・成長実感が一定の順序で連鎖すると、離職率の低下、現場の自律性向上、戦略実行スピードの加速などの効果が実証されています。
4. 生成AIとの共働モデル
仮説設計(行動前)・実行直前・振り返り(行動後)の各フェーズでAIが“問い”と“意味づけ”を支援。人間だけでは途切れがちな短期ループ(行動の手応え)と長期ループ(価値観の進化)の双方を日常業務の中で持続させます。これにより、「行動の見落とし防止」「多角的視点の付与」「振り返りの深度向上」が可能になります。5.二重の行動巡環モデル
短期の変化と長期の進化を同時に回す。1. 短期ループ(経験 × 関係性 × 意味づけ)
- 経験:小さな挑戦や成功が次のきっかけを生む
- 関係性:相手の反応や共感が信頼を深める
- 意味づけ:その出来事の価値を再確認する
2. 長期ループ(価値観進化のループ)
- 価値観 → 思考 → 行動 → 関係性 → 意味づけ → 価値観の再定義
- 繰り返しにより、組織と個人が持続的に進化
生成AIは、この二層構造の中で“問い”と“意味づけ”を持続させ、日常の小さな行動変化を文化の進化へとつなげます。
【理論体系 無料ダウンロード】
今回発表した「組織行動科学(R) 理論体系(全編PDF)」を、無料ダウンロードいただけます。- 実際のデータ分析手法と5理論領域の詳細
- 心理的リワード巡環構造の図解
- 生成AIとの共働モデル事例
- 導入企業の効果測定データ
「やればできるのに続かない」を変えるための実践的ノウハウを、ぜひ自社でご活用ください。
ダウンロードはこちら
d68315-140-316c5f52261d95e3a692645872c72e70.pdf目次:
- はじめに:成果と信頼は、関係性から生まれる
- 基本思想:組織とは“行動の連鎖”であり“関係性の質”で進化する
- 定義:組織行動科学(R)とは
- 行動巡環モデル:意味が深まり、行動が進化する構造
- 心理的リワードの構造|行動を進化させる“内なる報酬”
- 5つの理論領域|行動を支える構造的視点
- 生成AIとの共働|意味ある行動を共に支えるパートナーへ
- 巻末付録 : 組織行動科学(R)用語定義集
人は意志やモチベーションだけでは動き続けられません。組織行動科学(R)は、“あの人だからできた”をなくし、“この環境なら誰でも動ける”を実現します。生成AIとの共働により、問いと意味が巡る組織文化を全国の現場に広げていきたいと考えています。
リクエスト株式会社
Human Capital Development XR HRD(R) Team
E-mail:request@requestgroup.jp
※ リクエスト株式会社は、「Behave:より善くを目的に」を掲げ、国内338,000人の組織で働く人たちの行動データに基づいた組織行動科学(R)を中核ブランドとし、人間の行動と思考を研究開発する5つの機関が連携。これまで980社以上の人的資本開発を支援してきました。
https://www.requestgroup.jp/

【会社概要】
社名:リクエスト株式会社
所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目4番8号 京王フレンテ新宿3丁目4F
代表者:代表取締役 甲畑智康
事業内容:人的資本開発・生成AI活用支援
ブランド基盤:組織行動科学(R)
コーポレートサイト:https://requestgroup.jp/
代表プロフィール:https://requestgroup.jp/profile
会社案内ダウンロード:https://requestgroup.jp/download